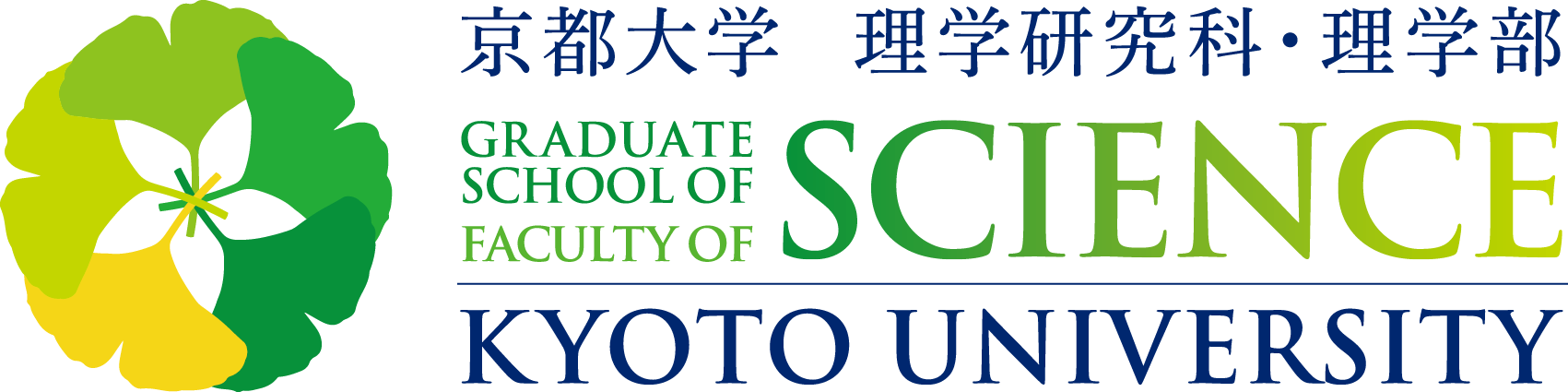本講演会は在職中53歳の若さで他界された玉城嘉十郎先生のご意志に基づいて、没後30年にあたり、ご遺族より奨学のために多額のご寄付をいただき開催されている、公開の学術講演会です。玉城先生は明治19年(1886年)にご生誕、京都帝国大学理学部において理論物理学を講じられ、その門下からは新しい分野を拓く数多くの物理学者が輩出されました。第1回は大学紛争のさなかの昭和44年(1969年)秋、湯川秀樹先生、朝永振一郎先生、寺本英先生を講演者に招いて開催されました。以後回を重ね、さらに2009年度より湯川記念財団からの寄付を得て共催となり、本年度は54年目、62回目の開催となりました。
講演のテーマは必ずしも既存の専門にとらわれず、明日の学問への展望をひらくものを、と心がけて選ばれています。この玉城記念講演会は、理学部・理学研究科及び学内の他研究科の学生、教職員、卒業生や元教員、学外の専門の研究者、さらには一般の方々まで幅広い聴衆を集めています。特に新型コロナウイルス感染症の影響のもと、オンライン開催が始まってからは、遠方からの参加者や中高生の参加者も現れ、また講演後も活発に質疑応答が行われております。
講演のテーマは必ずしも既存の専門にとらわれず、明日の学問への展望をひらくものを、と心がけて選ばれています。この玉城記念講演会は、理学部・理学研究科及び学内の他研究科の学生、教職員、卒業生や元教員、学外の専門の研究者、さらには一般の方々まで幅広い聴衆を集めています。今回は4年ぶりに完全対面で実施されました。
第62回玉城嘉十郎教授記念公開学術講演会は、2023年12月14日(木)午後2時より、京都大学北部総合教育研究棟1階益川ホールに、91名の聴衆が集まりました。玉城嘉十郎教授記念公開学術講演会 実行委員長の伊藤哲也 准教授(当時。現、教授)による開会の辞に続き、田中 耕一郎 理学研究科長から玉城嘉十郎先生の紹介、また、本講演会の第1回の様子の紹介や、その第1回の講演要旨を収録した、講演会50周年記念の書籍「京大理学部知の真髄-玉城嘉十郎の2つの遺産」(2022年12月30日発行)が紹介されました。
第62回となる本講演会の講演は、『数理物理から導かれる新しい幾何学』を共通テーマとして、入谷 寛 京都大学 大学院 理学研究科教授による「量子コホモロジーの幾何学」、望月 拓郎 数理解析研究所 教授による「ゲージ理論と非可換ホッジ理論」の2つで、約2時間にわたって91名の参加者が聴きました。最後に、湯川記念財団の九後 太一 代表理事から、玉城記念講演会開催の経緯や本講演会の感想について紹介されました。
量子コホモロジーの幾何学
京都大学理学研究科・教授 入谷 寛

1.シンプレクティック幾何の起こり
シンプレクティック幾何学はニュートンの古典力学やそれを発展させた解析力学(オイラー,ラグランジュ,ハミルトン)に端を発している.質量$m$の質点の運動は,$q$を質点の位置,$p=m \frac{dq}{dt}$ をその運動量とするとき,ニュートンの運動方程式 $$ \frac{dp}{dt} = 質点に働く力= -V'(q) $$ によって記述される.ここで$V(q)$はポテンシャル関数である.ハミルトンはこれを次のような形の微分方程式に書き換えた.まず,ハミルトン関数と呼ばれる2 変数関数$H(p,q)$を次のように定める. $$ H(p,q) = \frac{p^2}{2m} + V(q) $$
このときニュートンの運動方程式は $$ \frac{dp}{dt}=-\frac{\partial H}{\partial q}(p,q), \quad \frac{dq}{dt}=\frac{\partial H}{\partial p}(p,q) $$ というハミルトンの方程式と等価となることが容易に分かる.この方程式(ハミルトン系)は未知関数$p=p(t), q=q(t)$に関する微分方程式であり,上の形とは限らない一般の関数$H(p,q)$ に対して定義できるものである.
ハミルトン系では「最小作用の原理」というものが知られており,ハミルトン系の解はある作用汎関数の臨界点となる.簡単のため $p(t + 1) = p(t), q(t+1) = q(t)$ を満たす周期1 の周期解のみに考察を限定しよう.作用汎関数$\mathcal{A}_H$は周期関数$( p(t),q(t) )$の空間上の関数(汎関数)であって次で与えられる. $$ \mathcal{A}_H[p,q]=\int_0^1 p(t)\frac{dq}{dt}(t) dt - \int_0^1H(p(t),q(t))dt $$ 「最小作用の原理」によると,周期関数$( p(t),q(t) )$がハミルトン系の解であることと,それが作用汎関数$\mathcal{A}_H$の臨界点であることとが同値になる.運動量と位置$(p,q)$が値を取る空間(今の場合は$R^2$)は相空間と呼ばれているが,ハミルトン力学が展開できるために相空間がもつべき内在的な構造について考えてみる.$H=0$の作用汎関数は$\gamma(t) = ( p(t),q(t) )$を相空間$R^2$の中のループとみなすとき, $$ \mathcal{A}_{H=0}[p,q]=\int_{\gamma の張る\mathrm{disc}} dp \land dq $$ という形に書き換えられる.ここに現れる2 次微分形式$dp \land dq$を$R^2$のシンプレクティック形式と呼ぶ.一般に閉かつ非退化な2 次微分形式が与えられた$2n$次元多様体のことをシンプレクティック多様体と呼ぶ.この2 次微分形式(シンプレクティック形式)こそがハミルトン力学が展開できるための相空間の内在的な構造である.
2.量子コホモロジー
コホモロジーとは多様体に対してあるベクトル空間を対応させるものであり,多様体の連続変形で変わらない情報(トポロジー)を与える大変重要なものである.大雑把には,$m$次元多様体$M$の$k$次コホモロジー群 $H^k(M)$とは,$M$内の$m-k$次元の「境界を持たない形(サイクル)」で生成されるベクトル空間である.ただし,別の形の境界になっているものはゼロとみなす.例えば,2 次元トーラス(ドーナツの表面)の1 次コホモロジー群は2 つのサイクルで生成される2 次元ベクトル空間であり,また2 次元球面の1 次コホモロジー群は(球面上の1 次元サイクルは全て1 点に縮められるため)ゼロベクトル空間となる.
1980 年代にアンドレアス・フレアはシンプレクティック多様体のループ空間に対する半無限次元のコホモロジーを考えた.これが量子コホモロジーの起こりである.ここで多様体$M$のループ空間$LM$とは単位円$S^1$から$M$への滑らかな写像全体のなす無限次元空間である.正確にはループ空間ではなくその普遍被覆$\widetilde{LM}$を考える.$M$自体が単連結と仮定しておくと,$\widetilde{LM}$はループとそれを境界に持つ円盤のホモトピー類の組全体の集合として与えられる. $$ \widetilde{LM} = \{(\gamma, [g]) ∣ \gamma: S^1 \rightarrow M, g:D^2 \rightarrow Mは\gammaを境界に持つ円盤\} $$
先に述べた作用汎関数$\mathcal{A}_H$は$\widetilde{LM}$上の関数 $$ \mathcal{A}_H: \widetilde{LM} \rightarrow R, \quad \mathcal{A}_H(\gamma, [g]) = \int_{D^2}g^* \omega - \int_{S^1} H(\gamma(t))dt $$ を定める.ここで$\omega$は$M$上のシンプレクティック形式で,$H$は$M$上の関数である.先に述べたように作用汎関数の臨界点はハミルトン方程式の解である.フレアの理論では,臨界点のみならず,作用汎関数$\mathcal{A}_H$の勾配流を考える.これは$\mathcal{A}_H$を無限次元空間 $\widetilde{LM}$の高さを与える関数だと思ったとき,$\widetilde{LM}$上に置かれた「ビー玉」が落ちていく流れ,のことである.非常に雑に言うと,量子コホモロジーは$\widetilde{LM}$内の$\mathcal{A}_H$に関する安定多様体 ― $\mathcal{A}_H$の勾配流で流し たときにある臨界点に流れ着く点全体の集合 ― が与える半無限次元のサイクルたちがな すベクトル空間である.例えば$\mathcal{A}_{H=0}$の典型的な安定多様体は $$ \widetilde{LM}_+ = \{(\gamma, [g]) \in \widetilde{LM} ∣ g:D^2 \rightarrow M は概正則円盤で\gammaはその境界\} $$ で与えられる.これは次元も余次元も無限の「半無限次元」のサイクルであり,量子コホモ ロジー環の単位元に対応する.
3.量子体積
最後に筆者の最近の研究に触れたい.シンプレクティック多様体$M$の体積はシンプレクティック形式$\omega$を使って $$ Vol(M)=\int_M \frac{\omega^n}{n!} = \int_M e^\omega $$ と定義される.この体積の「量子化」を先ほどの半無限次元サイクル$\widetilde{LM}_+$上の積分として次のように定義したい. $$ QVol(M) = \int_{\widetilde{LM}_+} e^{\Omega - \mathcal{A}_{H=0}} $$
ここで$\mathcal{A}_{H=0}$は$H=0$のときの作用汎関数であり,$\Omega$は$M$上のシンプレクティック形式𝜔が自然に定める$\widetilde{LM}$上のシンプレクティック形式である.このような積分はアレクサンダー・ギベンタールによって1990 年代に考えられた.この積分は物理の量子場の理論における「経路積分」と呼ばれているものに対応し,数学的に厳密な定義はない.一方でグロモフ・ウィッテン不変量と呼ばれるものを使うと別の数学的な定義を与えることはできる.
例えば$M$を標準的な計量が与えられた2 次元単位球面としよう.球面の面積要素を𝑧軸方向に押し出したものは一様測度であることはよく知られている.つまり球面と領域 $a < z < b$との交わりの面積は$b-a$の定数倍になっている(ただし$-1\leq a \leq b \leq 1$とする).上の量子体積で同じことを考えると,$z$軸上の次のような測度が現れる. $$ \exp\left( -\sqrt{Q} (e^{-z}+e^z) \right) dz $$
ここで$Q=\exp(-Vol(M))$は球面$M$の体積を表すパラメータである.体積が大きくなる極限 ($Q\rightarrow 0$の極限)においてこの測度は$\left[ \frac{1}{2}\log Q, -\frac{1}{2}\log Q \right]$に台を持つ一様測度に近づくことが観察できる.量子体積の研究は始まったばかりであり,今後もっと面白い現象が見つかると筆者は期待している.
講演ではここで述べた量子体積とミラー対称性の関係,またGLSM(ゲージ化された線形シグマ模型)との関係にも簡単に触れた.紙面の都合上ここでは割愛する.
ゲージ理論と非可換ホッジ理論
京都大学数理解析研究所 教授 望月 拓郎

物理に由来する概念やアイディアが数学において独自に進化することがあります。その例として非可換ホッジ理論が挙げられます。非可換ホッジ理論では、基本群の表現やそのモジュライ空間、あるいは常微分方程式やその一般化であるD加群といった数学的な対象を研究しています。非可換ホッジ理論の出発点になったHitchin方程式は、物理のゲージ理論に由来します。そして、数理物理学のツイスター理論やミラー対称性の理論に影響を受けつつ発展しています。さらに、ツイスター構造の観点から、ホッジ理論やインスタントン・モノポールなどの対象を包括する理論が見えています。この講演ではその一端を紹介しました。
曲面$X$の点$p_0$を一つ固定した時、$p_0$から出発して$X$の中を通って$p_0$へ戻るような道を組$(X,p_0 )$の組のループといいます。連続的に変形できる二つのループを区別しない時は、ループというかわりにループのホモトピー類といいます。$(X,p_0 )$のループのホモトピー類全体は自然に群構造を持ち基本群と呼ばれます。基本群は曲面上の数学的対象の性質を理解する上で重要です。例えば、複素領域$U$上の線型常微分方程式の複雑さをはかるモノドロミーは$U$の基本群から一般線形群への表現と捉えられます。
境界を持たない閉じた曲面$X$の基本群の一般線形群への表現全体を考えることで得られる代数多様体$\mathcal{M}_B (X,n)$(指標多様体)はとても興味深い性質を持ちます。例えば、$X$にリーマン面の構造をいれると$\mathcal{M}_B (X,n)$の非可換ホッジ構造が定まります。この非可換ホッジ構造は物理に由来するHitchin方程式を考えることで得られます。
Hitchin方程式とは、物理のゲージ理論で重要な自己双対方程式から二つ変数を減らすことで得られる方程式を、リーマン面上の方程式に一般化したもので、1980年代半ばにNigel Hitchinによって導入されました。物理的な意義は明確ではなかったのですが、Hitchinは数学的な興味から研究を推し進めて実り豊かな世界を見出しました。その出発点となったのは‘コンパクトなリーマン面上のHitchin方程式の解(調和束)と基本群の表現とヒッグス束が同値’というCorlette-Donaldson-Hitchin-Simpsonの定理です。この定理によって、ヒッグス束のモジュライ$\mathcal{M}_\mathcal{Dol} (X,n)$と指標多様体$\mathcal{M}_B (X,n)$の同相(非可換ホッジ構造)が得られます。
さらに、調和束や非可換ホッジ構造をより深く理解するためにツイスター構造というものがCarlos Simpsonによって導入されました。この‘ツイスター’は数理物理学におけるツイスター理論に由来します。4次元ユークリッド空間$\mathbb{R}^4$上のインスタントン(自己双対方程式の解)と$\mathbb{R}^4$のツイスター空間上の実構造をもつ正則ベクトル束の間の同値を与えるPenrose-Ward対応というものがあります。この対応のキーになるのが、複素射影直線上の複素解析的なデータである‘重み0の偏極付純ツイスター構造’というものです。Simpsonは重み0の偏極付純ツイスター構造を用いて調和束を記述できることを洞察しました。これは局所的にはPenrose-Ward対応の次元簡約とみなせます。
ある微分幾何学的な構造をツイスター構造を用いて記述することは、単なる言い換えにとどまらない意義をもちます。ツイスター構造はホッジ構造というものの一般化であり‘ホッジ構造に関する概念や定理はツイスター構造に関する概念や定理に拡張されるはず’という指導原理(Simpsonのメタ定理)があります。ですから、ツイスター構造を用いて記述される微分幾何的な構造には、偏微分方程式の解という記述では見えないホッジ理論的な性質が見えてきます。例えば、代数幾何ではある対象から別の対象を作りだす操作が多数ありますが、ツイスター構造を用いて記述できるような微分幾何的な対象には、このような操作を適用できるようになることが期待できます。インスタントンに関する古典的なADHM構成や、Claude Sabbahと講演者によって展開されたツイスター$D$加群の理論がそのような例として挙げられます。このように代数幾何的な性質をツイスター構造によって強化すると、純粋に代数幾何的に証明することが困難な定理を、証明できるようになることがあります。ツイスター構造の観点から代数幾何的な対象や操作を強化するといったことに関しては未開の研究領域が大きく広がっており、興味深い課題が潜んでいると思っています。